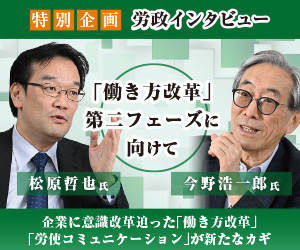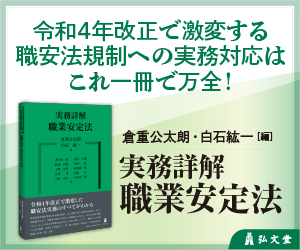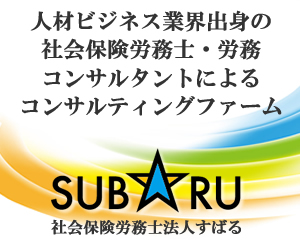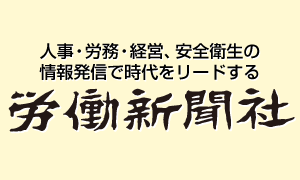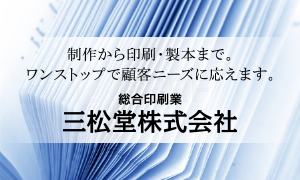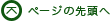公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第4回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(山川隆一座長)は14日、前回までに実施した関係団体のヒアリングを受けて、総合的な議論に入った。
ヒアリングに基づいた厚労省のまとめによると、主な審議内容は障害者雇用の質向上、農園型やサテライトオフィス型などで障害者と雇用企業の双方を支援する障害者雇用「代行ビジネス」の可否、就労支援A型事業所の位置づけ、難病患者ら手帳不保持者の扱い、100人以下企業に対する雇用納付金の対象拡大など。
雇用の質向上については、「客観的な指標が必要であり、障害者の立場からは研修制度、キャリア構築制度、ジョブコーチの配置などが必要」「雇用の量と質を一緒に高めるのは大変であり、当面は別々に推進していくべきではないか」などの意見が出た。
「代行ビジネス」については否定的な意見が多く、「差別禁止の観点からもこのビジネスが好ましくないことを当事者に伝えるとともに、なぜビジネスが拡大しているのかをもっと知る必要がある」「実態を詳しく調べたうえで、規制をかけたりガイドラインを作成すべきだ」「このままビジネスが拡大すると対応が困難になるため、対応を急いでほしい」などの意見が聞かれた。
難病患者らの雇用率算入については、「障害者手帳の所持を基本にしながらも、症状の不安定や痛みなど、手帳には現れない難病独自の就労困難性を"評価"する検討が必要」など。A型事業所については、現在は企業における業務内容と大差がない実態を踏まえながらも、「企業と同列に扱うのはどうか」との疑義も挙がった。
これらの意見を踏まえ、山川座長は(1)障害者雇用の質量拡大をどのような行政手法に取り込むかが課題(2)A型や代行ビジネスなどの実態把握の重要性(3)雇用率を含む各種支援制度との関係――に集約されると総括。次回からは...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。
【関連記事】
A型事業所や難病・疾病など5団体からヒアリング
厚労省の障害者雇用促進研究会(3月10日)