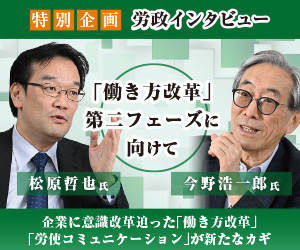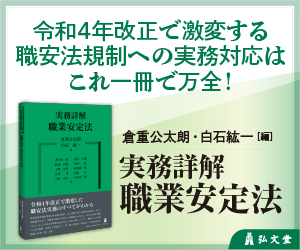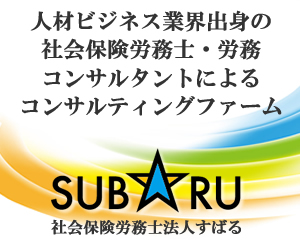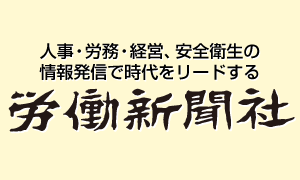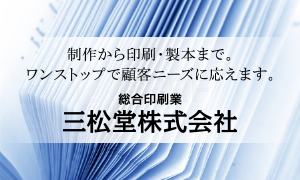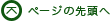Q 懲戒処分にはさまざまな種類があると思いますが、会社としてはどのように理解をして適用すべきでしょうか。
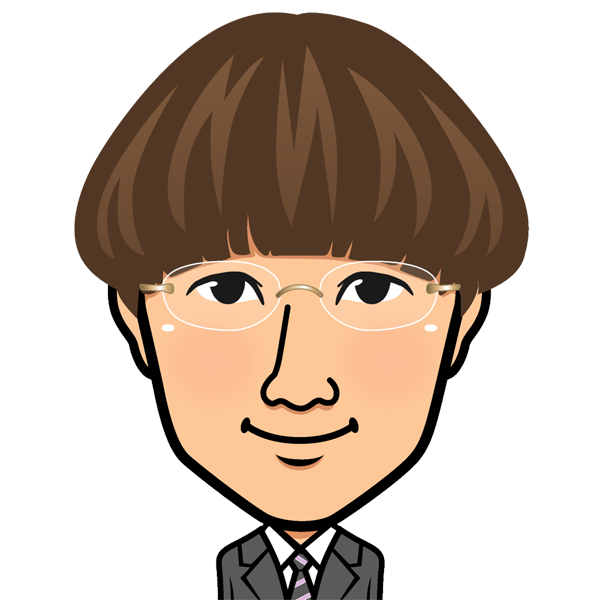 A いわゆる懲戒処分とは、従業員の秩序違反行為に対して課す制裁・罰則のことであり、原則としては就業規則に根拠を置くことによって発動することができます。ただし、労働契約法15条により、懲戒処分の内容が「客観的に合理的な理由を欠き」「社会通念上相当であると認められない」場合は権利の濫用として無効になるため、その規定や運用には十分な理解と慎重な対応が必要となります。
A いわゆる懲戒処分とは、従業員の秩序違反行為に対して課す制裁・罰則のことであり、原則としては就業規則に根拠を置くことによって発動することができます。ただし、労働契約法15条により、懲戒処分の内容が「客観的に合理的な理由を欠き」「社会通念上相当であると認められない」場合は権利の濫用として無効になるため、その規定や運用には十分な理解と慎重な対応が必要となります。
たび重なる労働法の改正や労働者のモラルの低下、ハラスメントや労使トラブルの増加、職場における人間関係などの複雑化などの状況により、企業がさまざまな指揮命令や教育指導の結果として、懲戒権の発動として懲戒処分を検討したり実行するような場面も少なくはなく、まさに労使関係をめぐる古くて新しいテーマだといえます。以下、代表的な懲戒処分の種類と内容を簡単に整理します。
| 戒告 | 通常は文書または口頭で厳重注意を行ない、今後の業務遂行に支障がないように将来を戒める処分。懲戒処分のなかで最も軽いもの。 |
| 譴責 | 一般的には始末書を提出させ、今後の業務遂行に同じ理由で支障を及ばせないように将来を戒める処分。 |
| 減給 | 本来支給されるべき賃金の一部を差し引く処分(制裁)。労基法91条により、1回の減給額は平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
| 出勤停止 | 一定期間の出勤を禁止する処分であり、出勤停止期間中は賃金が発生しない。通常は1~2週間以内が一般的。 |
| 降格 | 役職や職位、職能資格を引き下げる処分。経済的打撃が長期に継続するため、出勤停止よりも厳しい処分。 |
| 諭旨解雇 | 一定期間内に退職願の提出を勧告し、提出があった場合は退職扱い、なかった場合は懲戒解雇とする処分。 |
| 懲戒解雇 | 使用者が一方的に労働契約を解約する最も重い懲戒処分。解雇予告期間を設けない即時解雇にあたり、再就職に悪影響を与える傾向がある。 |
減給制裁をめぐる減給事由や減給幅については、さまざまな考え方があり、最近の裁判例としては、S社事件(東京地裁、令5.12.4)では、就業規則に減額の事由や変額幅を明示すべきと指摘する一方、N社事件(東京地裁、令6.3.29)では、賃金テーブルや人事評価、考課基準を説明会などで明示していれば認められると評価されています。
出勤停止をめぐっては、処分の対象となる具体的な行為と停止期間の長短のバランスについて紛争となることがあり、みずほ銀行事件(東京地裁、令6.4.24)では、長期間(4年以上)におよぶ自宅待機命令が無効とされた上で、会社側に慰謝料330万円の支払いが命じられています。
懲戒解雇をめぐっては、伊藤忠商事事件(東京地裁、令4.12.26)では、退職間近の従業員が約3000のデータを無断でアップロードしたことについて、営業秘密ではなかったものの転職先での使用が目的とされたことが不当と判断され、会社側に金銭損害が発生しなくても、懲戒解雇が有効とされました。
これらは令和に入ってからの裁判例の一部ですが、懲戒処分をめぐる裁判所の判断の傾向なども全体として意識しつつ、会社がやむなく最終手段として懲戒権を行使する場合の考え方やあり方について、必要な情報や認識を深めていきたいものです。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)