「信仰」の対象か、「鑑賞」の対象か
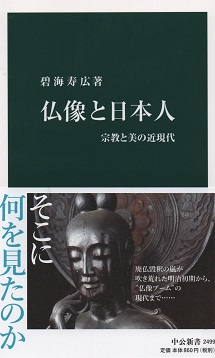 著者・碧海 寿広
著者・碧海 寿広
中公新書、定価860円+税
「仏像ブーム」だという。2009年に東京で開かれた興福寺の「阿修羅展」には100万人近い人が押し寄せ、大きな話題となった。その後も西国寺社からの「出開帳」はますます盛んで、彼らの貴重な収入源となっている。そんなブームに鋭い問題提起を試みたのが本書だ。
著者によれば、仏像とはもともとが「祈り」の対象であり、江戸期にも盛んだった「出開帳」も、基本的には江戸市民の信心に訴えた。ところが、明治初期の廃仏毀釈で存続の危機に立たされた仏像などの宝物が、「美術品」という新たな地位を得て、古美術鑑賞の対象となることで存続できた。それが紆余曲折を経ながら現代につながり、一大ブームを巻き起こすまでになっている。では、それまでの「信心」はどうなったのか。
本書は、仏像が「祈り」の対象か「鑑賞」の対象か、という古くからのテーマの考察。両者のせめぎ合いを象徴する、フェノロサによる法隆寺夢殿の救世観音開扉事件を皮切りに、和辻哲郎、亀井勝一郎、白洲正子、土門拳、入江泰吉らの文筆家や写真家を取り上げ、彼らの作品から見えてくる心象風景にまで分け入る。
著者は、現代のブームに対しては中立的な立場をとっているが、著名先人の著作に接し、実際に寺社を訪ね歩けば、自ずと答えがみつかるという考えのようだ。単なるガイドブックや鑑賞のノウハウ書ではなく、仏像論を通して現代日本人の内面に迫る重みが伝わってくる。 (俊)






















