患者目線を持った著名医師の「体験的」医療論
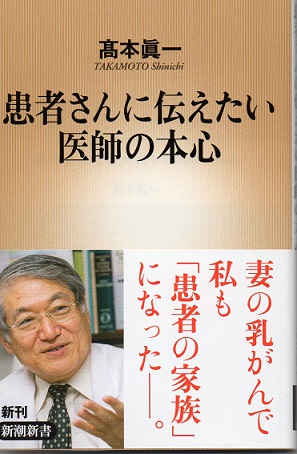 著者・高本 眞一
著者・高本 眞一
新潮新書、定価700円+税
日本の医療問題を考える場合、これまで常に中心にいたのは病院などの医療機関と医師だった。医師は頭が良くて偉い、治療は全て医師にお任せ、患者が文句を言うなんてとんでもないこと――。患者家族は長年に渡ってそう思い、当の医師らもそう思い込んできた。それがいかに誤った“幻想”であるか。本書は東大医学部出身で現三井記念病院院長という、日本の医療の頂点に立つ医師が真摯に語っている。
内容は「医師が『患者の家族』になったとき」など18章で構成、すべて著者が経験した「体験的医療論」だが、自身が家族をがんで亡くした経緯や、病院で「患者様」の呼び方を廃止した理由に始まり、医療事故と捜査当局の介入、病院のランク付け、浅薄なメディア報道、医学部の組織的欠陥など、現代の医療に関わる深刻な問題にも遠慮なく踏み込んでいる。
その底流に流れるのは「医師と患者は病気に立ち向かうパートナー」という考え。それ自体はそれほど新しいとは言えないが、問題は医師自身や医療界が実践しているかどうかだ。度重なる大病院の手術ミス、研究者と製薬業界の癒着など、繰り返される不祥事を顧みるに、患者と真に向き合う医師がまだまだ少ないのではないか、と思ってしまうのは評者だけだろうか。
全体の記述は非常に平易でわかりやすい。これなら、一般の読者はもちろん、医師への不信感を捨て切れない体験を持つ患者・家族らの心にも響くであろう。良心が直に伝わってくる1冊。(のり)






















