原爆と検閲を経て出た“記念碑”
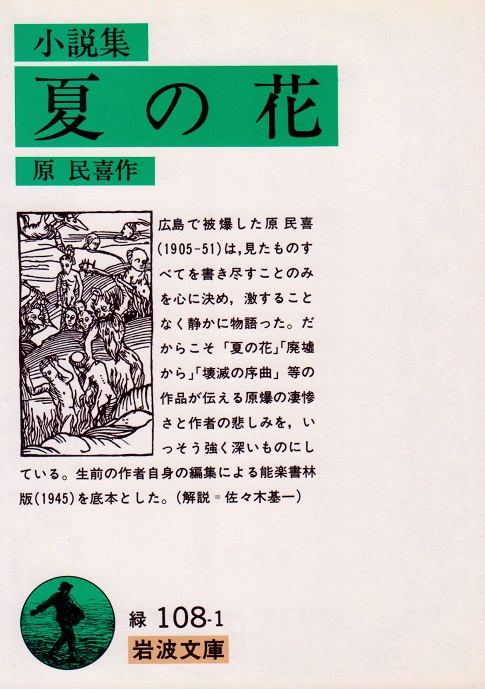 著者・原 民喜
著者・原 民喜
岩波文庫、定価600円+税
名作の多い「原爆文学」の中でも、本書はその嚆矢(こうし)となる短編だが、題名を見てピンとくる人はご年配か「三田文学」の関係者ぐらいになりつつある。だが、日本人が「戦争と平和」を考える際に、欠かせない1冊であることは確かだ。今は数社の文庫本になっており、著作権も切れたため、ネットでも読める。
著者は慶大英文科OBの作家で、広島市の親類宅へ疎開に来て被爆。郊外の親類宅へ避難する2日2晩の模様を描いた。爆心地を通り抜けたため、被爆直後の光景が余すところなく記録されているが、筆致は抑制的で透明感があり、所々に文学的な表現はあるものの、全体的には淡々と事実を書きとめている。「小説」となっているが、いわゆるルポに近い。
題名にも、時代状況が色濃く反映されている。原題は『原子爆弾』だったが、GHQ(連合軍総司令部)は原爆情報の公開を禁止していたため、そのタイトルと内容では検閲に引っ掛かる。そこで雑誌社を諦めて、文学同好会の色彩の濃い「三田文学」に変更し、タイトルもそれらしくない「夏の花」に変えて1947年6月、やっと世に出たもの。
原爆と検閲。本書の存在自体が、日本の敗戦がもたらした象徴的な出来事を体現している。想像力の乏しい評者は、本書を読んだ後、埼玉県東松山市の「丸木美術館」に何度か足を運んだ。文字と絵画を通じて沸き上がる「この世の地獄」から、死に行く人々のうめき声が聞こえる気がして、展示場から逃げ出したことも何度かある。
著者は被爆前に妻が病死、自身も被爆、その後の体調不良などが重なり、51年3月、46歳で鉄道自殺した。死ぬ前に知人らに遺書を送っていたが、その1人に三田文学の後輩で、パリ留学中の遠藤周作(96年死去)がいた。遠藤は64年にエッセイ「原民喜」を書き、「あれ以後、幾つかの原爆の日を扱った小説が出たが、『夏の花』に及ぶものは一篇もないような気がする」と書いている。(のり)






















