外交交渉を通じて見えた日本の命運
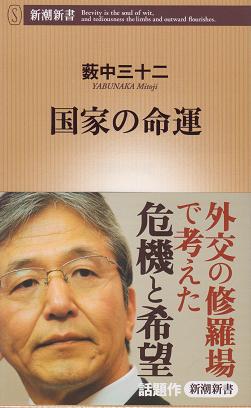
『国家の命運』
著者・藪中三十二
新潮新書、定価680円+税
著者は外務省キャリアのトップ、外務事務次官を昨年9月まで務めた官僚OB。本人も述べているように、常に対外交渉の第一線に立ち、交渉をまとめ上げてきたプロだ。その舞台裏を披露しながら、日本の国際プレゼンスの問題点を挙げ、未来に深い憂慮を示している。嫌でも「国益」というものを考えざるを得ない外交官の本音がかなり正直に出ている。
1980年代、日本は対米貿易摩擦の対応に追われたが、事務方として日米間を奔走したのが、当時の北米二課長だった藪中氏だ(外務省担当の経済記者として、評者も藪中氏に取材を繰り返した)。
巨額の対日赤字を抱えた米国側の「市場開放」要求は執拗で詳細を極めたが、これに対して「ノーと言えない日本」は「受け身」「言い訳」「小出し」に終始した、と述懐している。対外交渉の責任者にそう言われても困るのだが、米側の要求に「過剰反応」したマスコミの責任にも触れており、耳の痛い部分はある。
著者はそうなった要因として、戦後のキャッチアップ型経済成長を達成した日本の感度の鈍さ、政策の継続性とタテ割り構造から動こうとしない官僚機構などを挙げている。当の官僚OBがそう言うのだから、これほど確かなことはないが、問題はそれから20年以上も過ぎた現代日本の姿がほとんど変わっていない点だ。
日米摩擦の当時から、著者は「日本は変わらなければならない」と危機感を強めていたが、結局はなにも変わらないまま、世界は冷戦構造から多極化構造に移行。気がつけば、日本は少子高齢化、借金財政、世界に無関心な内向き志向といったマイナス材料ばかりが増えており、著者は「このままでは“国家の命運”にかかわる」として執筆に至ったのではないか。そんな思いが強く伝わってくる1冊だ。
本書を読めば、「弱腰外交」「情報の取れない外務省」など、野次馬的な批判だけでは何も生まれないことを確信させる。 (のり)






















